知っておきたい耐震基準の話
『その建物、いつ建てられましたか?』
2024年の能登半島地震以来、建物の「耐震性」への関心がさらに高まっています。
実は、不動産の価値やリスクを考える上で、この建築年月日が非常に重要な意味を持っていることをご存じでしょうか。
震度6でも倒壊しない!新耐震基準が生まれた日
新旧の耐震基準の大きな転換点は、1981年(昭和56年)6月1日です。
旧耐震基準(1981年(昭和56年)5月31日までに建築確認完了)の建物は、震度5程度の揺れでも倒壊しないことが目標とされていました。
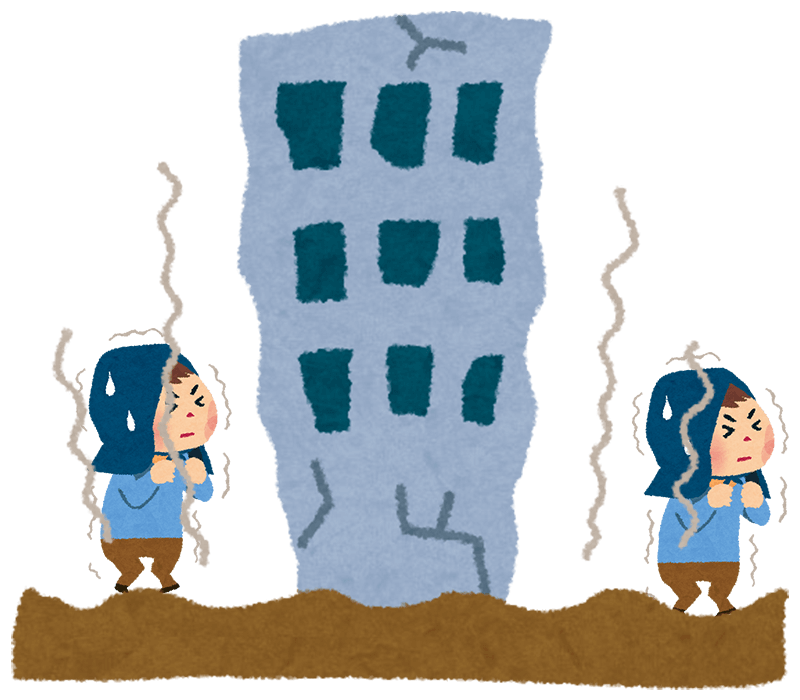
一方、新耐震基準(1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認完了)では震度5で軽微な損傷、震度6~7の大地震でも倒壊しないことが求められます。
※施工の数年前より新耐震基準を踏まえた行政指導が行われていたそうです。そのため旧耐震基準の建物でも、新耐震基準を満たしている可能性があります。
築古物件でも大丈夫?資産価値を高める意外な方法
耐震基準のみならず、築年数の古い建物は、入居者や購入希望者から敬遠されがちです。また、金融機関の融資が通りにくいなど、資産価値が下がる要因にもなりかねません。
しかし、ご安心いただける選択肢もいくつかございます。例えば、お住いの建物に「耐震診断」や「耐震改修」を施すことで、安全性の向上とともに、資産価値を高めることが可能です。
また、診断や改修にかかる費用を補助する制度や、税制上の優遇措置を設けている自治体もあります。
これらの制度を利用することで、費用負担を軽減できる可能性もあります。
2026年4月1日以前に変更があった場合でも、義務化の対象となります。つまり、施行日より前に変更があった場合でも対象となり、経過措置として2029年3月31日までに登記申請を行う義務があります。
まずは現在の建物状況を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。私たちが不動産の専門家として、最適な資産活用プランを一緒に考え、ご提案いたします。(宮本)
ニュースレター
最新記事
ニュースレターカテゴリ
不動産コンサルティング
不動産管理
ニュースレター最新5記事
地主・家主の皆様、
税理士・公認会計士の皆様のために、
私たちができること
弊社では、専門スタッフがお客様のニーズにお応えし、
適切なご提案とお手伝いをいたします。

貸宅地企画提案書
を作成致します
弊社は、地主・家主の貸宅地に関する問題を調査分析し、適切な対策をたてる為の企画提案書を作成しています。
- 地主・家主の皆様へ

資産税の
お手伝いを致します
税理士・公認会計士の皆様が相続税の申告をされる時や、顧問先に相続税の納税・節税などのご提案される時に、資産税のお手伝いを致します。
- 税理士・公認会計士の皆様へ







